|
植民地の異人-- 『大いなる遺産』と『種の起源』を中心に --
中 村 隆ディケンズ(Charles Dickens)1 の『大いなる遺産』(Great Expectations)は、雑誌『年々歳々』(All the Year Round)の1860年12月より 、翌年の8月にかけて週刊分冊の形で連載された。一方、20年にも及ぶ長大な思索の 末にダーウィンの『種の起源』(The Origin of Species)が1859年の11月24日に上梓 される。ダーウィンがディケンズの作品を少なからず愛好していたことは知られてい るが、2 今のところ、両者の間に強い影響関係があった と見なしうる確たる証拠はない。むしろ、それぞれに当時の文学界と科学界を代表し た両者は、少なくとも表面的にはほとんど没交渉であったように見える。3 しか し、両者間を繋ぐ糸が必ずしも、ないわけではない。本稿はその繋ぐものが何であっ たかについて考察する試みである。それは、二人の円熟期を代表するほぼ同時期の二 つの著作に埋め込められたある主題を検討することにより明らかにすることが可能だ と考える。具体的には、『大いなる遺産』と『種の起源』という相互に無関係に存在 しているように見える作品を取り上げ、このかけ離れた二つの点を結ぶ一つの明瞭な 線の存在を同定し、同時にそれを当時の社会や政治の文脈の中で考察したいと思う。 ダーウィンの『種の起源』がきわめて独創的な知見と思考に貫かれた科学の書である ことは論を俟たない。しかし、ダーウィンが自説の公開に躊躇しているうちに、マレ ー群島で自然の観察を続けていたアルフレッド・ウォレス(Alfred Wallace)はダーウ ィンのものと酷似した自然選択の理論に行き着く。それは、「変種がもとのタイプか ら無限に遠ざかる傾向について」("On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Type")と題された論文にまとめられ、ダーウィ ンに送られた。ウォレスの論文をダーウィンが受け取ったのは1858年6月12日のこと である。ダーウィンはそこに記されたウォレスの理論と自説との類似性に驚愕し、こ れが結果的に『種の起源』の執筆を早めることになる。4 しかし、この二人の博物学 者における意見の一致は、単なる偶然の所産として片づけることはできない。ダーウ ィンの『種の起源』で展開された理論は、ある特定の「時代精神(Zeitgeist)」に規 定されていた可能性が残されているからである。少なくとも、『種の起源』はそれが 生まれた時代から超絶して立つ孤高の存在ではなかったことは明らかである。例えば 、その影響の度合いの強さに関して意見の違いはあるものの、『種の起源』はマルサ スの『人口論』(An Essay on the Principles ofPopulatation, 1798)に少なから ぬ触発を受けて書かれた。それは、ダーウィン自身が認めるところである(興味深いこ とに、ウォレスもまたマルサスの『人口論』に影響を受けたことが知られている)。 5 『種の起源』における最重要語の一つである「生存競争("Struggle for Existence")」という言葉のヒントになったと言われているのがマルサスのおよそ次 のような主張である。 人口は抑制されないなら、25年で倍増する。言い換えれば、人口は等比級数的に増え る。しかし、食糧の増産率はよく見積もっても、算術級数を超えない。したがって、 食料の増大を超えて増えようとする人口には抑止力が働く。その人口を抑止するもの が、積極的抑制で、それは疫病、戦争、飢饉などである。これに結婚すれば生活が困 窮するという見込みのもとに結婚を控える予防的抑制、すなわち道徳的抑制が加わる 。6また、生物の変異や進化に関する議論は、周知のように、ダーウィンに先行して、彼 の祖父エラズマス・ダーウィン(Erasmus Darwin)が『動物誌』(Zoonomia)という詩 の中で1790年代半ばに展開している。その中で、彼は生物の進化は獲得形質の遺伝に よると述べている。エラズマスより数年遅れて、1801年に、フランスの博物学者ラマ ルク(Jean Baptist Lamarck)がキリンの首で有名な獲得形質の遺伝という見解を提 出した。この両者は、生物の変異が環境に影響を受けること、また獲得形質は遺伝す るということを述べた点で注目すべき一致を見せている。7 また、ダーウィンがケンブ リッジ大学に在学中に読んだペイリー(William Paley)の『キリスト教の証拠』 (Evidences of Christianity, 1794)や『自然神学』(Natural Theology, 1802)も 『種の起源』に影響を与えている。例えば、ペイリーは、『自然神学』の有名な冒頭 部で、精巧な造りの生物を精密な時計になぞらえ、時計職人なくして時計が出来ない ように、精密な構造を有する生物は造物主としての神なくては考えられないと論じた 。このようにして神の存在を論証したペイリーの議論は、逆に、生物における精密な 構造の原因や由来という問題をのちにダーウィンに提起することになった。8 さら に、ダーウィンはその議論の底の浅さを批判しているが、1844年に匿名で出版され、 ベストセラーとなったチェインバーズ(Robert Chambers)の『創造の自然史の痕跡』 (Vestiges of the Natural History of Creation)もまた生物の変化と進化につい ての物語を含んでいた。9 以上のように、ダーウィンの『種の起源』に影響を与えたであろう存在は複数あり、 いずれも当時の社会に、その後も引き続き甚大な影響を残すことになった。とりわけ 、マルサスの政治経済学は、ベンサム(Jeremy Bentham)の功利主義と結びつき 1834年の「救貧法改正」やパノプティコンという新たな監獄制度の着想を生み、イギ リスの社会に深く還流することになる。10 また、ヴィクトリア朝的な「進歩史観」が露 骨に現れた、ダーウィンに言わせると「哲学」のないチェインバーズの『創造の自然 史の痕跡』が一大ベストセラーになったことに象徴的に示されているように、神の創 造の物語ではなく、生物が主体となる進化の物語を比較的容易に受容する土壌はイギ リス19世紀に確かに存在していた。このような生物進化の概念を受け入れる時代の雰 囲気は、当時の歴史観と少なからず関連している。それは、大別すると二つに分けら れ、一つは、ホイッグ史観とも呼ばれるマコーレー(Thomas Babington Macaulay)に 代表される歴史観で、人類の歴史は直線的に上昇・発展しているとする「進歩史観」 である。もう一つは、カーライル(Thomas Carlyle)に典型的に現れる「循環史観」で 、これは、歴史を一つの生物のアナロジーで捉え、文明は誕生し、成長し、衰退する と考えた。人間および人類の文明は常に前進・進歩すると考えた前者のホイッグ的進 歩史観が、生物の変化を提唱する進化論と親和性があったことは容易に推測できる。 ただし、注意すべきは、進歩史観とダーウィンの考えた進化論モデルは似かよってい るが、明瞭な相違点があることである。なぜなら、進歩史観は、進化を一本の単純な 梯子を昇る直線的なモデルとして捉え、その頂点に人間を置いたが、ダーウィンはそ のような「楽観的な」前進主義的直線のモデルを否定し、枝分かれモデルを提唱した からである。11 さて、ビア(Gillian Beer)のすぐれた研究が示すように、ダーウィンの『種の起源 』で展開される「物語」と呼応する物語が時に、反発を内包しながら、テニスン (Alfred Tennyson)や、キングスリー(Charles Kingslay)や、ジョージ・エリオッ ト(George Eliot)や、さらにはハーディー(Thomas Hardy)の内に現れた。 それで は、当時の文壇の寵児であったディケンズと、ダーウィンの『種の起源』はいかなる 関係を取り結ぶのであろうか。すでに幾つかの批評・研究が、ディケンズとダーウィ ン(主義)との関係を考察しているが、その数は決して多いとは言えない。例えば、フ リント(Kate Flint)は『大いなる遺産』と『種の起源』の関係を論じて、両者の間に 見られる共通の言語に着目し、『大いなる遺産』の中に、ダーウィン的な思想や用語 (例えば、競争、生き残り、人間の野獣性、カニバリズム等々)を読み込む。12 あ るいは、レヴァイン(George Levine)は『ダーウィンと小説家たち』の中で、ディ ケンズとダーウィンの間に見られる共通点に関して、細部への徹底的なこだわりを挙 げている。またディケンズの小説はありふれた日常の奥に潜む異常性を暴き出す側面 があり、その意味で日常を「異化("defamiliarization")」するが、これもダーウィ ンの『種の起源』に特徴的に見られることである。なぜなら、ダーウィンもまた、変 化していないように見える個々の生物の裏に常に激しく変異する可能性を秘めた生物 を描いているからである。ディケンズの小説はまた、多様な人間であふれているが、 この生物的な活力に満ちた個が生みだす圧倒的な多様性なども、ディケンズとダーウ ィンに共通に見られる、とレヴァインは指摘している。そしてこの多様で一見、何の 関係も、脈絡もなさそうに見える個と個が実は相互に依存しあい、繋がっているとい うことを明らかになるのが、ディケンズの小説であり、ダーウィンの『種の起源』に おける理論である。ただし、このように個と個が繋がっていることが明らかになるよ うな「偶然("chance events")」が顕現する時、ディケンズにおいては表層の奥に隠 された神秘的なものが暗示されるのに対し、ダーウィンでは神の計画が否定される点 で両者は決定的に異なっていると、レヴァインは述べる。13 また文学研究家とは別にボウラー(Peter Bowler)のような科学史家が現在、精力的に ダーウィンとヴィクトリア朝文化との関係について研究を発表している。しかし、科 学史家の主たる関心はダーウィンの学説の再検討や科学的意義、またその学説の哲学 的背景にあり、したがって、マルサスやスペンサー(Herbert Spencer)といった思想 家は比較的よく取り扱われるが、作家ディケンズが登場することはまれであるし、取 り上げられてもその扱いは決して大きくはない。14 よって、必然的に、ディケンズとダーウィンという研究テーマは、主に英文学批評の 枠組みの中で取り上げられることになる。その結果、生ずるのは、ディケンズの特定 の作品や幾つかの作品の中に、ダーウィンの理論の骨子をなすようなキー・ワードや 、またはダーウィンの思想と対応する類似の言語などを読み込むことである。つまり 、進化論という科学の思想は、いったん言語のレヴェルに還元され、文学作品におけ る進化論的な意味を内包する言葉が吟味されていく。先述したフリントやレヴァイン の研究、およびビアの『ダーウィンのプロット』などがそうである。これらの先行研 究は、19世紀英文学と進化論の類似と相違、あるいは親和と不協和をヴィクトリア朝 の文化的なネットワークの中で読み取り、文化の支配的な言説を跡づけた点で、すぐ れた研究である。この方面ではビアの研究に最良のものが示されていると思われるが 、ビアはダーウィンとヴィクトリア朝中期から後期にいたる文化における進化論的な 言説、あるいはこの時期の文化の共通の土壌を検証する。ビアは言語は不可避的に比 喩的であり、科学の書も言語が媒体となっているという点で、必然的に濃密な比喩で できていると考える。したがって、『種の起源』は完全に文学作品と同列に論じうる 文化的なテクストである。例えば、『種の起源』の主張の一つに「すべての生物は無 限に連なる鎖のように結びついている」というメッセージがある。ビアは、この連鎖 のイメージとヴィクトリア朝に広く好まれた「クモの巣」、「樹木」、「迷路」等々 の語彙を対応させる。そうすることで、ヴィクトリア朝文化を通底した一つの水脈を 発見する。15 しかしこれらのビアを嚆矢とする研究に不満 がないわけではない。それは、最終的には、すべてが言語の問題に帰着することであ る。ヴィクトリア期に共通の文化的な土壌があるとしたら、それを語彙やコンセプト に還元するのも一つの方法には違いないが、それとは別の可能性も残されているので はないだろうか。私はその別の方法として、時間を共有した文化のテクストに普遍的 に内在させられた政治・社会的な主題(テーマ)について考察してみたい。本論では 、ディケンズの『大いなる遺産』とダーウィンの『種の起源』という二つの作品を当 時の社会と政治との関連において考察し、そうすることにより見えてくるある共通の 政治・社会の文脈を検討したいと思う。結論を示唆するならば、それは両者における 奴隷と植民地をめぐる意識あるいは無意識と関係している。端的に言えば、エディプ ス・コンプレックスならぬ「植民地コンプレックス」とでも言うべきものが両者を繋 ぐ糸となる。
まずは『大いなる遺産』に内包された物語を振り返ることにしよう。この小説には幾
つかの、時に相矛盾しあう物語が埋め込まれている。大きな枠組みで捉えると、この
小説はピップという主人公の少年の、子供時代から青年期に至る人生の経緯を恋愛の
蹉跌を交えて語っている点で「教養小説」("Bildungsroman")の伝統を踏まえ
ている。また、細分化すると、ここには同時に徒弟の物語がある。ピップは、物語が
始まった時点ですでに両親がなく姉のジョー夫人(Mrs.Joe)に養われているが、彼女
の夫は鍛冶屋でありピップはここで義兄のジョー(Joe)のもとで鍛冶屋の徒弟として
人生が始まるべく用意されている。この鍛冶場にはもう一人、オーリック(Orlick)と
いう奉公人がいるが、オーリックはピップの姉のジョー夫人を金槌で殴り瀕死の重傷
を負わせる典型的な悪い徒弟である。一方、ピップは義兄であり主人でもあるジョー
を慕い、ジョーもピップを深く愛しているのでピップは良い徒弟の型にはまる。した
がって、徒弟の物語は、さらに特定すると、良い徒弟と悪い徒弟の物語になる。これ
は18世紀の諷刺画家ホガースの一連の版画のテーマであった。16 し
かしピップは徒弟の生活を半ばで終えることになる。なぜなら、彼の前には謎の遺産
提供者が現われ、彼を「紳士」にするための不思議な計画が明らかになるからである。
その結果、ピップは故郷の田舎の村を離れ、ロンドンに出る。ロンドンで彼は放蕩が
過ぎ、一時借金苦に陥るがやがて成年に達し、そのため、もたらされる(分割支払いの
)遺産は高額になり、彼はルームメイトであり、親友のハーバート(Herbert Pocket)
の事業を陰ながら援助する。その意味でこれは美しい友情の物語である。青年のピッ
プはやがて少年の頃からの憧れの女性と結婚したいと思うようになるが、その相手は
故郷の謎の老婦人ミス・ハヴィシャム(Miss Havisham)の邸の養女である氷のように
冷たい心をしたエステラ(Estella)である。しかし、この恋は成就しない。エステラ
は資産家のドラムル(Bentley Drummle)という性悪の青年を選び取り、結果的に不幸
な結婚生活に入るからである。一方、ピップはエステラを失い、たび重なる借金のた
めについに逮捕されるが、その苦境はジョーによって救われる。こうしてすべてを失
い、故郷の村に帰ってきて初めて、彼の良い理解者であった若い女性ビディ(Biddy)
の存在に気がつくが、時すでに遅く、ビディは男やめもとなった義兄のジョーとまも
なく結婚する。つまりこれは二重に失われた不幸な愛の物語でもある。 ところで、マグウィッチに幽霊のイメージを執拗に重ねていく手法に明らかなように、 ディケンズの小説には「おとぎ話」("fairy tale")」の要素が色濃く、多分に現実離 れしている点は多くの批評家の認めるところである。17 例えば、『大いなる遺産 』においては、老女ミス・ハヴィシャムを取り巻く世界は、止まった時計、朽ちて色 褪せた花嫁衣裳などの舞台装置と相俟って、不気味で超現実的な雰囲気を漂わせてい る。彼女の創造の原型には明らかにおとぎ話の「魔女」がいる。しかし、他方、ディ ケンズの小説が、ヴィクトリア朝という時代に強く規定された、ある種のリアリズム を保持していたこともまた否定しえない事実である。ディケンズの小説の舞台は主と して、小説執筆期と近接した時代のロンドンであり、したがって、小説がヴィクトリ ア朝という時代そのものに拘束されることは避けられないことだった。ヴィクトリア 朝という時代背景が見える二,三の例を『大いなる遺産』の中から挙げるなら、例え ば、この小説が採用している「自伝」という形式がある。ギルモア(Robin Gilmour) は、ヴィクトリア期に、多くの小説や詩、あるいは文芸批評や神学が「自伝的な欲求 」("autobiographical pressure")に駆られていたことを指摘している。それは、当 時の人々の関心を集めていた進化論と深く関係する現象だった。なぜなら、進化論は 、起源や由来に関する科学の物語であり、一方、自伝は自己の起源や由来を記述する 文化の形式に他ならなかったからである。進化論は、自己の起源や由来を知りたいと いう当時の人々の欲求を喚起した。その一つの現われが、言語表現形式における自伝 の流行を招くことになった。18 また、秘密裡にロンドンに帰ってきたマグウィッチが自己の犯罪歴をピップとハーバー トに語る興味深いくだりがある。それによれば、マグウィッチは刑務所の入所と出所を 三たび繰り返している。そして、そこで刑務所に入れられたマグウィッチは、自分の頭 を測られる(".. . they measured my head . . . they had better a measured my stomach.. . ." [III, III, 345])。19 ここで、なぜマグウィッ チが頭の形やサイズを測定されたのかを理解するためには、当時流行していた骨相学 ("phrenology")のことを知っておかねばならない。骨相学は、頭蓋骨の形から人間の 性質を推量した、19世紀中葉に流行した疑似科学である。これはのちに、19世紀末に なると、ロンブローゾ学派の犯罪人類学に合流することになる。つまり、マグウィッチ と、犯罪と、骨相学という一連のヴィクトリア朝の文脈が、『大いなる遺産』のこの 短い記述の中にはめ込まれている。このエピソードは、(ディケンズの)小説がいか に具体的な歴史を切り取り、作品の中にそれを盛り込むかを示す好例である。20 マグウィッチに関しては、この小説全体と深く関係すると思われるもう一つの重要な歴 史的相関物がある。それが、18世紀末から19世紀中葉にかけて、イギリス本国の囚人 たちの流刑地としての役割を担っていたオーストラリア植民地である。オーストラリ アに初めて流刑囚を乗せた船が到着したのは1788年のことである。以来、1840年代に かけて、陸続と囚人たちがオーストラリアに送り込まれた。それは、1783年のパリ条 約によって、アメリカ合衆国の独立が承認されたため、北アメリカ植民地に代わる流 刑地としてオーストラリアが選ばれたからである。またイギリス国内で犯罪が急増し 、監獄が払底していたからでもあった。21 流刑囚は、刑事犯であることもあれば、反政 府運動や労働運動で逮捕されたいわゆる政治犯であることもあった(マグウィッチは前 者である)。マグウィッチはシドニー(Sydney)近郊のニュー・サウス・ウェールズ植 民地(New South Wales)に送られている(ただし、ニュー・サウス・ウェールズは 1840年に流刑囚の受け入れを拒否しているので小説の時代設定をするなら、小説が書 かれた1860-61年よりも20数年ほど前に置くことができるかもしれない)。22 このようにピップと彼をめぐる遺産に焦点を据えて、物語の筋立てを見ていく時、こ の小説の深部に植民地をめぐるどこか暗い物語が隠されていることに気づく。小説が 書かれていたイギリス19世紀中葉は、イギリスにおける第二帝国の時代("Second British Empire")の完成期23 にあたる。それは、イギリスが狭い島国から 解き放たれ、貪欲に版図を拡大した時期であり、ヨーロッパ列強と覇を競いつつ、イ ンドで、アジアで、アフリカで、アメリカ大陸で、そしてオーストラリアとニュージ ーランドで、植民地経営を確立した時期である。しかし同時に、反乱が頻発し、その 矛盾が露呈した時期でもあった。そして、植民地は不可避的に、複雑な意味を含有す ることになった。そこは本国("Mother Country")の暴力的な国家権力が顕現する地 であり、力の論理が正義であり、劣等と見なしうる有色民族を差別し、キリスト教を 含めた自己の文化を強制的に押しつける独善的文化帝国主義の発現する場所であった 。同時に、マルサスが指摘したように、植民地は余剰人口("redundant population")の捌け口であるとともに、増大する人口を支えうる資源や食料が豊富に 蔵する供給地でもあった。24 『大いなる遺産』における植民地の問題を考える時、流刑の地オーストラリアから帰 還したマグウィッチが小説においてどのように描かれ、どのような機能や位置が付与さ れているかを検討することは有効であろう。明らかに、マグウィッチはこの小説におい て、オーストラリア植民地という具対物を通して、当時のイギリスの帝国主義全般と 深く関連する一連の比喩形象を形成しているように思われるからである。マグウィッチ は流刑囚であるにせよ、彼はともかくオーストラリアで成功をおさめ、ピップに巨額 の資金を提供した張本人である。それにもかかわらず、資金の出所を知ったピップは 、その金を不正なものと見なし、マグウィッチを穢れた存在として捉える。しかし、ピ ップはマグウィッチから逃げることが倫理的にできない。なぜなら、ピップに匿名で、 金を送り続け、彼を「紳士」に仕立て上げたのは、他ならぬマグウィッチだからである 。ピップは帰還したマグウィッチを見て、異常なまでの恐怖心にとらわれ、マグウィッ チを、メアリー・シェリーの『フランケンスタイン』の「怪物」のイメージで見たり (III,I, 337)、あるいは、マグウィッチに「野蛮人」のイメージが付与される。マ グウィッチにおける野蛮が暴かれるのは、マグウィッチを変装させようとピップが悪戦 苦闘する場面に現れる。マグウィッチは何を着せても似合わないし、変装させようとす ればするほど、マグウィッチは「犯罪者」の相貌を現し、「野蛮人」のように見えてし まう(III,I, 336)。 さらに、罪人マグウィッチに「黒人」の意味合いがそれとなく重ね合わされていること にも注意すべきだろう。それは彼が吸うタバコの名称に暗示的に示される。マグウィッ チの好んで吸うタバコの名は「黒人の頭」("Negro-head" [III, I, 329 ])と呼ば れているからである。ここでは、付属物で主体の性質を暗示するという比喩の技法が 働いていると考えられる。ディケンズにおける比喩の特徴的な使用(一例を挙げるなら、ディケンズの "as if" の異常に頻繁な使用)はつとに知られている。例えば、ヒリ ス・ミラー(J. Hillis Miller)は、ディケンズは人間の性格描写にあたり、しばし ば衣類のような付属物で置き換えることを指摘している。25ここにもし、その換喩的な 技法(metonymy または synecdoche)を認めるとするなら、作者はマグウィッチを黒人 のメタファとして捉えていると考えられる。だとすると、今まで見たきたマグウィッチ に付与される属性には一連の関連した意味の連鎖がある。罪人、流刑囚、野蛮人、そ して黒人という言葉は、マグウィッチが追放された先の「新世界」、オーストラリア植 民地と呼応する響きを有しているからである。とりわけ植民地と黒人のイメージの連 関は興味深い。19世紀初期から中期にかけて、奴隷問題は当時の植民地の大きな問題 であったからである。
『大いなる遺産』におけるオーストラリア植民地、より広義にはこの小説とイギリス の帝国主義との関係について考察する前に、イギリスの植民地政策の歴史的経緯を簡 単に振り返ることにしてみたい。イギリスはスペイン無敵艦隊を撃破したエリザベス 朝ルネサンスの時代より伝統的に、世界に冠たる海洋軍事大国であった。その海洋軍 事力を背景に、1600年に東インド会社が設立される。そして、インドで生産される胡 椒などの香辛料貿易が展開されることになる。その後、イギリスからの移民が1630年 代に北米植民地の建設を始め、17世紀中葉にはイギリスはバルバトス島とジャマイカ 島を獲得し、サトウキビの栽培を開始する。また、1672年に設立された「王立アフリ カ会社」(Royal African Company)を基盤として、奴隷貿易が本格化し、「三角貿易 ("triangular trade")」が始まる。この時、黒人奴隷は、西インドのバルバドス、 ジャマイカ両島でのサトウキビのプランテーションの労働力源となった。西アフリカ から大量の黒人奴隷が西インド諸島へ連れてこられ、26彼らはそこできわめて安価 な労働力となり、砂糖が生産された。そして砂糖がイギリスでブームを呼んでいた紅 茶のために消費された。27また、イギリスの植民地形成において特筆すべ き役割を果たしたのは、1701年から1713年のユトレヒト条約までの13年間のスペイン 継承戦争と、1756年から1763年まで続いたヨーロッパ列強間の7年戦争である。スペ イン継承戦争においてイギリスは、スペインからジブラルタルとミノルカを得て地中 海交通の要所を押え、同時に黒人奴隷供給権を手に入れた。また、フランスからはニ ューファウンドランドとアカディアを得た。特に、ニューファウンドランドは世界有 数のタラの漁場であるばかりでなく、イギリス海軍の重要な基地となった。他方、7年 戦争は、プロイセン、イギリス同盟と、オーストリア、フランス、スペインの同盟と の間の戦争であったが、イギリスでは、大ピット(Pit the Elder)がこの戦争を指揮 し、イギリスを勝利に導く。そして1763年のパリ条約によって、イギリスはフランス からカナダとミシシッピ川以東の地域を奪取する。また同様に、フランスから、西イ ンド四島、セネガル、ミノルカを得た。さらにイギリスはスペインから、フロリダを 割譲される。この間、1757年にはプラッシーの戦いでクライヴ(Clive)率いるイギリ ス軍は、フランス・ベンガル連合軍を破り、インドにおけるイギリスの支配を確立し た。こうして、イギリスは18世紀の中盤以降までに、インド、北アメリカ、西インド 諸島、西アフリカを手中におさめた。28 続けて、ナポレオン戦争を経て、その戦後処理のウィーン会議(1814-15年)でヨー ロッパ列強間で領土の分割が行われるが、この時イギリスはフランスに西インドの二 つの島とアフリカの植民地を、またオランダにはジャワをそれぞれ返還したものの、 セイロン(スリランカ)、シンガポール、喜望峰、モーリシャス島、地中海のイオニア 諸島とマルタ島といった海事上の重要拠点を確保する。29こうして、世界規模のイギ リス第二帝国の建設が着々と進められる。この第二帝国建設にあたっての理論的支柱 となったのは、ウェイクフィールド(Edward Gibbon Wakefield)の「計画的植民地政 策」("systematic colonization")であった。ウェイクフィールドの議論は、計画的 に植民地に移民を送り込み、植民地に適宜資本を投下し、そこに眠る資源を活用し、 本国にそこから上がる利潤を還元しようというものであった。これは計画的な移民に よって、国内の貧困問題の原因となっている過剰な労働力を整理し、同時に本国が植 民地を管理しようとするシステムである。これに対立する議論もあり、それはコブデ ン(Richard Cobden)とブライト(John Bright)で有名なマンチェスター学派により唱 えられた。それによれば、植民地は貴族的な統治者と、莫大な数の駐屯軍を必要とし ており、贅沢な浪費に過ぎない。したがって、植民地はむしろ「我々の首にまとわり つく石臼」("millstone of our necks")であり、植民地との関係を絶つべきとの主 張である。30しかし、このような対立意見にもかかわらず、 結果的には、イギリスの植民地は膨張する。19世紀前半のイギリス第二帝国を支えた のはまず、イギリス、インド、中国間の新「三角貿易」であった。この貿易で、イギ リスは中国から茶を輸入し、他方、もともとはインドの特産品であった綿製品を工業 力を背景にイギリスが大量生産し、インドに輸出した。そしてインドで生産されるア ヘンを中国に輸出した。この時、すでにイギリス東インド会社はアヘン専売権をムガ ール皇帝より奪い取っていたが、直接に中国に輸出したのではなく、貿易商人を通し て間接的な取り引きをした。茶の輸入の代価としてイギリスは中国に銀を支払い続け てきたが、今や、国内で不足していた銀の代わりにアヘンで事足りることになった。 こうしてイギリス領インドはアヘン貿易で潤い、インド植民地政府は多額のアヘン税 収入を得た。そしてイギリス政府には莫大な茶税と、中国の銀貨がもたらされた。し かし、アヘンは麻薬であり、アヘン中毒患者の急増は国家を滅ぼす危険があった。清 朝政府もただ手を拱いていたわけではなく、再三にわたり、アヘン輸入禁止令を出し た。そして、ついに林則徐によるイギリス商人からのアヘン没収が引き金となって、 イギリスと中国の間で1840年にアヘン戦争が勃発する。1842年8月に南京条約が結ば れ戦争は終結するが、その条約の内容は、中国に完全に不利な不平等条約であった。 この結果、中国は多額の賠償金を払い、香港をイギリスに割譲し、広東、厦門、福州 、寧波、上海の開港を余儀なくされる。中国の敗北は明らかだった。 また「計画的植民地政策」によって、1830年以後に、カナダ、オーストラリア、ニュ ージーランド、南アフリカといった白人植民地に移民が続々と送り込まれる。その結 果、イギリス本国を出た移民の総数は1830年には5万5千人だったものが、1840年代と 1850年代には、毎年25万人もの数になった。特にオーストラリアでは、金鉱が見つか ったことからゴールドラッシュが起こり、1852年だけで、8万人の移民が移住した 。3131 アヘン戦争に示されるように、19世紀初期から中期において、イギリス統治下の植民 地に多数の反乱があったことは注目すべき事実である。1776年にアメリカ北部13州の 独立宣言がなされ、その前後の独立戦争を経て、1783年のパリ条約でアメリカの独立 が承認されるが、イギリス本国とアメリカ植民地の対立の引き金は、1765年の「印紙 条例」という課税制度であった(1773年には、「茶条例」が発布され、さらにアメリ カの反イギリス感情を煽ることとなる)。アヘン戦争以外で主だった造反・反乱をあ げるなら、同じ中国で、1857年から1860年にかけてアロー戦争が起こった。また、他 に目を転じるなら、1816年に西インドのバルバドスで、1823年、1824年、1830年にや はり西インドのジャマイカで、1830年に西インド諸島に近い南米北東のギアナで、ま た、1824年から1826年までと、1852年に都合二度ビルマで、1837年にカナダで、 1838年から1842年にかけてアフガンで、1843年にパキスタンで、1856年にはペルシャ (イラン)で、19世紀前半には7度にわたり喜望峰東部地域のカフィールで、1846年 にはニュージーランドで、そして1858年にはインド北部で反乱(セポイの反乱)がそ れぞれ起こっている。32そして、セポイの反乱以後は、インドにおいて 東インド会社による間接統治は終わり、イギリス政府は直接統治に移行し、インドと ビルマを掌握した。 これらの反乱ではたいてい武力による威嚇や鎮圧がなされたが、これが強圧的な政策 とするなら、融和的な政策もないわけではなかった。それが、1807年の奴隷貿易の廃 止と、1833年の奴隷制度の撤廃である。奴隷反対運動は基本的にはメソディズムやク エーカーといった新興キリスト教の福音主義("Evangelicalism")の人道的な立場か ら出発している。奴隷制度撤廃の運動を指導したのはメソディズムの開祖ウェズリー (John Wesley)や、彼を引き継いだ国会議員のウィルバーフォース(William Wilberforce)、そしてG.シャープ(G.Sharp)、クラークソン(Clarkson)らの博愛人 道主義者だった。331822年にはイギリス国内の全国組織として「奴 隷制の改善と段階的廃止のための協会」がクラークソンによって設立され、ついに奴 隷制は1833年にイギリス帝国全域にわたって廃止される。 有色人種の原住民を管理する植民地においては概して、武力を背景とする統制がなさ れたが、19世紀の中葉には、カナダ、オーストラリア、ニュー・ジーランド、ケープ ・コロニー(南アフリカ)といった白人移民を主とする植民地では、自由主義的な方 針のもとに、当該植民地での責任政府("self-government")の自治を認知する方策が 取られた。このような緩やかな政策の裏には、二つの理由が考えられる。一つは、文 化的に劣る「異人」であり、また「野蛮人」である原住民を統治する時とは違い、白 人が占める植民地は、いわば同胞の住む場所であり、弾圧するよりは、懐柔策を取る ほうが賢明と考えたからである。もう一つは、本国にとって、植民地の防衛のための 費用が負担になってきており、したがって、責任政府を許可することによって、植民 地というテリトリーの保護を自己負担させる狙いがあった。 以上、見てきたことから本論にとって重要となる19世紀初期から中期における植民地 のイギリス人に対する意味合いを集約するなら、植民地は、その積極的価値と、消極 的価値という相矛盾する価値観の中で揺れ動いていたと言うことができるように思わ れる。積極的価値とは、植民地は砂糖や茶や綿花に代表されるように本国に富や生活 の豊かさをもたらす打ち出の小槌であったということと、インドや中国に示されるよ うに、植民地はイギリスの工業製品の巨大な消費地を提供したということである。そ の反面、イギリスの富の蓄積は、黒人奴隷を非人道的な形で利用し、インド人や中国 人から搾取するという民族差別のシステムの上に成立していた。これが植民地の負の 遺産である。先述したように、イギリスは1672年に「王立アフリカ会社」を設立し、 黒人を奴隷化する国家的な体系を構築して以来、アフリカから西インド諸島に大量の 黒人奴隷を送り込んだ世界最大規模の黒人奴隷消費国であった。他方、19世紀に入る と、イギリスは世界に先駆けて奴隷売買を禁止し、さらに奴隷制度そのものを廃止す る。「ヨーロッパ最大の黒人を狙う密猟者」から、「模範的な奴隷廃止論者」への変 貌、これを、ウォルヴィン(James Walvin)は、「パウロの改宗("Pauline conversion")」と呼んでいる。34この非人道的行為から人道主義への矛盾に満ち た180度の転回に際して、イギリス国民の心の奥底に、植民地をめぐるやましい過去 というコンプレックスが形成された可能性は充分に考えられるのである。 ともあれ、奴隷制度の廃止を推進したのが、新興キリスト教の福音主義と、1832年の 選挙法の改正に伴ってできた改革議会であった。しかし、1834年にイギリスで、院内 救済に一本化し、貧民を厳しく管理する「新救貧法」が成立したことからもわかるよ うに、そしてディケンズがまさに『オリヴァー・ツィスト』(Oliver Twist, 1837-38)でその救貧法を糾弾し、最下層の貧困を描いたことからも察せられるように 、西インド諸島の黒人奴隷を救おうという運動の只中にあって、イギリス国内には貧 困が蔓延していた。そこから、植民地の奴隷問題よりも、まず国内の貧困問題が先決 ではないのかという議論が当然のごとく噴出する。『大英帝国の興亡』(The Rise and Fall of the British Empire, 1994)を書いたジェイムズ(Lawrence James)は、この対立を福音主義者の伝道師たちの博愛主義のイデオロギーと、軍人と 植民地政府役人らによる実務家("pragmatists")の冷めた現実的なイデオロギーの対 立として捉えているが、この博愛主義と現実主義の対立を端的に物語ることになるの が、1865年のジャマイカにおける暴動である。これは奴隷制廃止の皮肉な結果である ジャマイカでの黒人の失業問題に端を発していた。現地の黒人がイギリス統治政府の 役人と軍人を数名、殺害するという事件が起こったが、それは暴動とは言えないほど の出来事だった。しかし、当時のジャマイカ総督のエドワード・エア(Edward Eyre) の脳裏には、セポイの反乱(1857-58年)の悪夢がよぎったのか、彼はこれを大規模 な反乱の兆しと見て取って直ちに戒厳令を敷き、同時に強力な報復と制裁を断行する 。その結果、数百名の黒人が絞首刑となり、多数の黒人がむち打ちの刑を受けた。さ らに、銃殺を嘆願する逮捕者の願いを聞きいれず、仲間同士で絞首刑をかけさせたり 、バプティスト会派の黒人牧師を処刑したりするという残酷な仕打ちをした。イギリ ス国内の最初の世論は、迅速な行動に出て、ジャマイカ在住の1万5千人のイギリス国 民の命を守ったということでエアを英雄扱いしたが、彼の残酷な仕打ちが明らかにな るつれ、過剰な報復であるとの批判が出されるようになり、イギリス国内の博愛主義 者たちがエアを殺人罪で告訴せよとのロビー活動を行った。そのため、エアの行動を 審議するための委員会が急遽作られ、国を二分するような議論が闘わされることにな る。この時、エアを弁護する側についた著名人には、カーライル、チャールズ・キン グスリー、ラスキン(John Ruskin)、テニスン、そしてディケンズらがいた。告発 する側についたのが、例えば、ミル(J.S. Mill)、ハクスリー(T. H. Huxley)、ダー ウィンだった。エアを弁護する典型的な議論は、事の発端(失業問題)は黒人の怠惰 に由来すると述べ、さらに黒人の邪悪さ、不道徳をあげつらい、黒人の消し去ること のできない「野蛮」な性質を指摘することだった。35つまり、黒人奴隷制度の廃 止から30年経てもいまだに黒人を単なる文化の欠如した異人・野蛮人と見なす多数の 人間がいたことをこの事件は示している。むしろそれが多数派だった可能性が高い。 なぜなら、ヴィクトリア朝の名だたる文学者がエアを擁護する側に回っているからで ある。結局、エアは罷免されるが、刑事告発はされなかった。ディケンズの浩瀚な伝 記を著したカプラン(Fred Kaplan)は、ディケンズはこの時、募金活動をしたり、公 開討論会に出たりといった積極的な行動には出なかったが、それでも、ディケンズが 有色の原始的な人間に対して偏見を持っており、白人優越主義があったことは否定で きないと述べている。36しかも、この「エア論争」("the Eyre debate")の起きる10年以上も前の小説『荒涼館』(Bleak House, 1852-53) で、ディケンズはジェリビー夫人(Mrs. Jellyby)というアフリカに強い関心を寄せる 女性を登場させているが、彼女は「アフリカより近いものは目に入らず」、ニジェー ル沿岸の「ボリオブーラ・ガー」という理想的な黒人植民地のことばかり考えている 女性である。そのため、彼女は家の中は散らかし放題で家事は一切せず、最終的に家 族を不幸に落とし入れる。ここに、当時の福音主義者たちの奴隷反対運動へのディケ ンズの皮肉があることは明らかである。植民地の不幸の前に、国内の不幸があるはず だという「実務家」のイデオロギーをディケンズは有していたことになる。
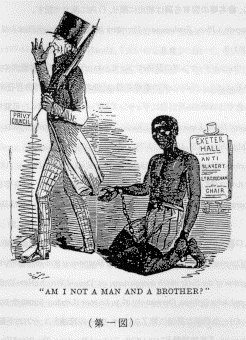 ところで、当時、ヴィクトリア朝の福音主義と博愛主義の象徴的建造物がロンドンに あり、それは「エクセター・ホール」と呼ばれる集会場だった。この「エクセタ・ホ ール」が黒人奴隷問題との関係で登場する、『パンチ』に掲載された興味深い絵があ る(第一図参照)。37『パンチ』は1841年7月17日に創刊されたヴィ クトリア朝の有名な諷刺漫画週刊雑誌であるが、まず第一図は一見して明らかで簡潔な メッセージを持っている。この図は、『パンチ』の1844年6月1日号に掲載されたもの で、鎖に縛られた黒人奴隷が描かれている。この黒人奴隷の言い分は「私だって人間 です、私はあなたの兄弟ではありませんか?」というきわめて直截的なメッセージ( 奴隷解放運動のスローガンで、ダーウィンの母方の祖父ウェッジウッド[Josiah Wedgwood]の造語)38となっているが、その下の説明書きは、次の通 りである。「エクセター・ホールでの記念集会が昨日、開かれた。ブルーム卿はその 集会の会長を務める予定だったのだが……[集会では]書記が5月10日の枢密院と題さ れたブルーム卿の手紙の抜粋を読んだ。それによれば、『私は枢密院で議長を務めな くてはならないので出ることができない。これは、国民の福祉のために必要なのだ。 』」ここで注意したいのはその日付である。先に記したように、奴隷制度が国会決議 を経て、イギリスで廃止されるのは、1833年のことで、この1844年の記念集会とは、 したがって、奴隷制廃止の記念集会である。しかし、10年たっても鎖につながれた奴 隷が描かれているということは、奴隷(のイメージ)はイギリス社会から消し去られ ていなかったことを意味する何よりの証拠である。例えば、西インドで開放された奴 隷、すなわちアフリカ系黒人はイギリスの都市に集結し始めていた。また、イギリス から独立したアメリカ合衆国で奴隷制度が廃止されるのはこの諷刺漫画の掲載からお よそ20年後の1863年のことである。絵柄を見ると、鎖で縛られた黒人奴隷が後ろ向き のブルーム卿(Henry Peter Brougham)の上着の裾を引っ張ろうとしている構図で あり、ここから、黒人奴隷に対する白人の冷淡と、同時に後ろめたさの相反する気持 ちを読み取ることができる。ブルーム卿は、奴隷解放運動の中心人物であったウィル バーフォースと親交があり、イギリス最高の司法の地位である大法官(Lord Chanchellor)にまで昇りつめた人物で、熱心な奴隷制廃止論者として知られていた。 同時に彼は枢密院司法委員などの要職も歴任しており、1860年には教育の普及と奴隷 制の廃止に尽力したとの理由で王室より爵位を授けられている。39奴隷 制廃止記念集会よりも、枢密院の会議を優先させたかもしれないが、奴隷制反対論者 として知られたブルーム卿を、ここに敢えて登場させたことに、『パンチ』の作者の 痛烈な皮肉が込められている。結局は、博愛主義は身振りにすぎないのではないか、 偽善ではないのか、そういう根源的な批判を私たちはこの図から読むことができる。 さらに、後ろ向きで逃げようとしているブルーム卿を、イギリス紳士一般のメタファ と考えるなら、奴隷制をめぐるイギリス本国の国民に内在する意識を推し測ることも できるだろう。つまり、イギリス植民地における奴隷は、できれば避けて通りたい、 あるいはふれられたくない過去の汚点だったということである。19世紀中期に現われ た、時代のある空気を反映している可能性の高い『パンチ』の一枚の漫画は、したが って、植民地と不可避的に結びつけられる黒人奴隷のイメージ、そしてそれを忌まわ しい過去として認識し、できれば避けて通りたいが、同時に後ろめたいという、ねじ れた良心の呵責を表象している。フロイト的に言うならば、植民地と連想されるイギ リス帝国におけるごく最近の過去の汚点としての黒人奴隷は、無意識下に抑圧したい 一種のトラウマを形成したのかもしれない。このような植民地をめぐる良心の呵責と それを抑圧しようとする無意識的な心理操作を、私は仮りにヴィクトリア朝中期の「 植民地コンプレックス」と呼びたいと思う。すがる黒人奴隷から逃げようとするブル ーム卿の絵に刻まれたもの、それはおそらくこの時期に深く潜行し、抑圧された無意 識であり、それが、ディケンズの1860-61年の作品である『大いなる遺産』にも隠蔽 されていると考えられる。それが端的に示されるのは、『大いなる遺産』の冒頭部の マグウィッチである。マグウィッチはそこで、第一図の黒人奴隷と酷似した姿で現われ る。彼は脱走した囚人であり、重い鉄の足かせを引きずっているのである。
 さらに、『大いなる遺産』と植民地を考える上で示唆を与えてくれるものとしてやは り『パンチ』からもう一枚の漫画を見てみたい(第二図参照)。これは、 1857年の9月12日号に掲載された絵で、言うまでもなく、同年に勃発したインドにお けるセポイの反乱の寓意図となっている。この戦いでは多数のイギリス兵が戦死して おり、したがって、怒り狂ったブリタニア(イギリス帝国を象徴する女神)がセポイ (インド傭兵)を荒々しく踏みにじり、剣を振りかざす構図が描かれている。しかし 、目を惹くのは怒り狂うブリタニアよりも、むしろ、画面右下に描かれている殺され ようとしているセポイの妻たちとおぼしき女性たちの悲痛な姿である。ある者は恨め し気にブリタニアを見上げ、別の、胸を露わにした女性は顔を下向きにそむけている 。また裸の幼児を必死に抱きかかえている母の姿が描かれている。では、ここに描か れている図の主題は、イギリス人の怒りなのだろうか、それともインド人の恨みや悲 しみなのだろうか。それを一概に断ずることは容易でない。しかし、この第二図を、 先に見た第一図と並べてみると、時代的には10年以上の隔たりがあるにもかかわらず 、その構図の驚くべき類似性に気がつく。すなわち、ブリタニアをイギリス紳士ブル ーム卿に、ブリタニアの右下で悲嘆に暮れる傭兵の妻たちを鎖に縛られ、ブルーム卿 のコートの裾を引こうとしている黒人奴隷に重ね合わせると、その構図は寸部も違わ ぬほど似てくる。この時、ブリタニアの剣はブルーム卿の傘に見えなくもない。また 、両者の足の構え、右腕を上げている構図なども一致している。何よりも、傭兵の妻 たちはブリタニアのスカートの裾を引っ張ろうとしているようにも見え、これは恨め し気にブルーム卿の上着の裾を引っ張ろうとする黒人奴隷と見事に重なり合う。つま り、表面的には怒れるブリタニアを表意しているように見える第二図にも第一図と同 様の「植民地コンプレックス」が隠蔽されていると見ることができる。激しく暴力的 に搾取しながら、あるいは実際に植民地において暴力を行使しながら、同時に後ろめ たさや良心の呵責にとらわれる、そういった相反する意識の葛藤=コンプレックスを 『パンチ』の二枚の漫画は私たちに示している。 先に、ディケンズは『荒涼館』で、ジェリビー夫人という人物造型を通して、福音主 義者の奴隷制反対運動を痛烈に皮肉ったことを述べた。しかし、ディケンズにヴィク トリア朝中期の『パンチ』の二枚の絵に刻印されているような植民地コンプレックス はなかったのだろうか。『荒涼館』については稿を改めて別の機会に論じなくてはな らないが、次の章では『大いなる遺産』における植民地コンプレックスの存在を考察 してみたい。
植民地の奴隷問題に関して、福音主義の博愛のイデオロギーに対し、植民地の不幸よ りも国内の貧困が先決であるとの実務家の現実主義のイデオロギーがあったことを指 摘したが、ディケンズが例えば『オリヴァー・ツィスト』であれだけ下層の貧困の問 題を扱ったことから見て、ディケンズが人間の不幸一般に敏感な感覚を持っていたこ とは容易に推測できる。したがって、植民地の黒人の不幸をディケンズが見聞きして 、なお完全に素通りできたと考えることは逆に、不自然であり、ディケンズに植民地 コンプレックスがあった可能性は高い。無論、『大いなる遺産』に直接的な形で黒人 奴隷は登場していないが、すでに何度か見てきたように、マグウィッチは明らかに黒人 奴隷的な属性を付与されている。例えば、物語の冒頭のマグウィッチの描写には、すで に見た『パンチ』の黒人奴隷との類比を読み取ることができる。それは次のような場 面である。 "Hold you noise!"cried a terrible voice, as a man started up from among the graves at the side of the church porch. "Keep still, you little devil, or I'll cut your throat!"両親の眠る静かな墓地で追想にふけっていたピップ。彼の前には広い湿地帯が広がり 、遠くには鈍い色を放つ川が見え、遠くの海からは風が吹きつけてくる。そこに突然 現われた恐ろしい男。静かで寂しげな風景が一瞬にして動的で緊張に満ちた場面に変 わる。男はピップに言う。「静かにするんだ。小悪魔め。喉を切り裂いてやるぞ。」 男は足を引きずっていた。足には大きな鉄かせがある。彼はまたずぶぬれで、泥にま みれ、傷だらけである。そして、にらみつけ、うめきながら、身体を小刻みに震わせ 、歯をガチガチと鳴らしている。ここに描かれているのは、脱走した囚人には違いな いが、同時に、看取されるイメージは『パンチ』で見た手を鎖で縛られた黒人奴隷の ものと似ている。ただ違うのは、『パンチ』の奴隷がおとなしそうなのに対し、この 囚人はきわめて狂暴なイメージを有していることである。しかし、ここで、囚人に植 民地の奴隷の象徴を読み取るなら、彼の凶暴性は不思議ではなくなる。植民地は反乱 と暴動の可能性を不可避的に内在させており、実際に反乱は何度も起きているからで ある。囚人は罪のない幼いピップを「小悪魔め!」と罵っているが、この囚人(マグ ウィッチ)が植民地奴隷の意味を包含すると考えるならば、暴力的に搾取する側に立つ 本国にいるものすべては、「悪魔」的存在であるのかもしれない。そして、何よりも 、この「イラクサに刺され、野バラに身を切られた」マグウッチは蔑まれ、虐げられ る人間のイメージを背負っている。このように鉄のかせで縛られ、血を流す囚人マグ ウィッチは、植民地で強制的にアフリカから連行され、西インドで過酷な肉体労働を課 された黒人奴隷のイメージと符合する。『大いなる遺産』はその物語が始まった時す でに、囚人、虐待、黒人奴隷、植民地という一連の意味の連鎖があった。 ここで、植民地との関連で、マグウィッチにおけるある特徴的な行為に注目してみたい 。それは、彼の変装(偽装)という行為である。マグウィッチが黒人奴隷という植民地 の暗部を象徴する存在であるならば、マグウィッチにおける変装は、無意識やコンプレ ックスと関係すると考えられる。フロイト(Sigmund Freud)は、無意識は、「転移 ("displacement")」と「圧縮("condensation")」という二つの方法によって加工さ れたのち、夢の中に顕在化することを指摘しているが、40マグウィッチにおける文字 通りの変装という行為が、作者の植民地コンプレックスを反映させているように思わ れる。第一義的には、マグウィッチはイギリス国内で正体を見破られないために、変装 を余儀なくさせられるのであるが、ただそれのみが理由ではない。ディケンズにとっ て、マグウィッチは知らず知らずのうちに、できれば意識に昇らせたくない、言い換え るなら、無意識の境界に抑圧したい植民地と奴隷の象徴となっていたに違いないので ある。しかも、「エア論争」で露呈したように、ディケンズは「白人優越主義者」と しての側面を持っていたことを考え合わせるなら、イギリス帝国主義下の植民地にお ける黒人奴隷の問題は、いわば、作者にとって忌まわしい過去の記憶、すなわち、心 の傷(=トラウマ)になっていた可能性があり、したがって、そのトラウマの象徴で あるマグウィッチは直視したくない存在であった。そのために、あれほどピップはマグ ウィッチに再会して脅えるのであり、作者はマグウィッチを変装させ、隠したいのであ る。物語の最終第三巻で、ピップは、終始マグウィッチを隠そうとしてあれこれ画策す る。第二巻の最終章でマグウィッチは、嵐の夜に闇にまぎれて突然、ピップの前に現わ れるが、ピップはまずマグウィッチの正体を周囲の者に対して隠そうとする。そのため 、ピップは叔父が田舎から突然、訪ねてきたのだと嘘をつく。偽名、偽装、変装そし て嘘、これらのものを総動員してピップはマグウィッチのアイデンティティを歪曲し、 隠蔽しようとする。 このピップによって隠蔽されるマグウィッチとはまた別に、小説の第三巻で、マグウィ ッチと結びつけられている注目すべき機能に、マグウィッチが果たす謎解きの要素があ る。その意味で、彼は物語の最後に登場し、もつれた糸をほぐすギリシア劇の deus ex machina(機械仕掛けの神様)の役回りを演じる。彼が小説中に再び 登場することによって、解かれる謎は都合、三つほどある。まず第一の謎は、ピップ に遺産を提供していたのは誰かという問題である。それはミス・ハヴィシャムではな く、マグウィッチだった。その時、半信半疑のピップにマグウィッチは言う。「その遺 産の額は、5という数字で始まるのではないかな?」それを聞いてピップは凍りつく。 確かに彼が受け取る遺産の年額は500ポンドだった。続けて、マグウィッチは言う。「 その遺産は代理人を通してもらっているだろう。それはJ で始まる人間ではないかな ?」確かに、代理人の弁護士の名は、Jaggersであり、ピップは自己の勘違いに気が つく。同時にそれまでの自分の夢 ― 遺産を提供してくれていたはずのミス・ハヴィ シャムの許可を得て、彼女の養女エステラと結婚すること―が崩壊するのを感じ、ピ ップはよろよろと倒れる(以上、II, XX, 316)。植民地の流刑囚であったマグウィッチ が、本国のピップに資金を提供しつづけ、ピップを紳士に仕立て上げたという事実も また、マグウィッチが当時の植民地の意味を深く内蔵させた象徴であることを示す。植 民地の主たる機能の一つは、本国に富をもたらすことである。西インドからもたらさ れた砂糖、あるいは、アヘンの代価として中国がイギリスに支払った膨大な額の銀(貨 )、そして、オーストラリアからもたらされた良質の羊毛(メリノ・ウール)などの豊 かな富や資源を思い浮かべるなら、そのことが了解されるだろう。富の出所を知った ピップはしかし、言いようのない衝撃に打たれる。もしここで、主人公ピップと作者 を重ね合わせ、それをピップとエステラの愛の文脈ではなく、植民地の文脈で捉え直 すなら、ピップの衝撃の隠された意味がより明瞭になるかもしれない。砂糖は西イン ド諸島の黒人奴隷のいわば血と汗から生じたものであり、アヘンの代価としての銀は 、中国の民衆を欺き、苦しめることによって得たものである。さらに、羊毛は流刑地 オーストラリアからもたらされ、流刑囚の多くはマグウィッチがそうであるように牧羊 に従事していた。資本家による暴力的な搾取の構造が本国と植民地にはあったが、強 欲な資本家たるイギリスはしかしながら、被抑圧民である植民地の人間(有色人種) に負い目や引け目がなかったはずはなく、それは1807年の奴隷貿易の廃止と1833年の 奴隷制度の撤廃に結びついた。ここに見え隠れする植民地と奴隷をめぐるコンプレッ クス―抑圧したい過去の記憶―が、ディケンズという19世紀の作家を通して、マグウ ィッチを生み出した。したがってマグウィッチが指示するもの、それは、イギリス第二 帝国の植民地と被差別奴隷民のイメージが引き起こす罪の意識、あるいは贖罪の思想 である。そしてこの贖罪のテーマは、マグウッチを外国航路の汽船に乗せて、逃亡さ せようとしたピップの計画が挫折した後で、ピップが獄中のマグウィッチに示す深い 献身に見ることができる。ピップは再び獄中の人となったマグウィッチを彼の死の日 まで、毎日尋ねていき彼を慰め、その死を看取る。そして、ピップはこの時、マグウ ィッチに対する「悪感がすべて解けてなくなる」(III, XV, 443)のを感じる。また、 救出の際に深い傷を負ったマグウィッチに、刑務所も寛容であり、マグウィッチを付 属の病院に収容し、手錠をほどいてやる。このように、深い痛手を負ったマグウィッ チに示す、イギリス紳士のピップの献身愛とイギリス国家の寛容は、搾取され傷つい た植民地に対する、イギリス本国に内在する贖罪の願望を表象すると解釈できるかも しれない。ともあれ、最期になってようやくマグウィッチに示されるピップの感傷主 義すれすれの献身愛は読者にある種の感動を与えることは確かである。 第二の謎は、作品を通して不気味な存在であり続けるサティス館(Satis House)の奥 に隠棲する老女ミス・ハヴィシャムをめぐる謎である。ピップが初めてミス・ハヴィ シャムに出会った時、彼女は朽ちた花嫁衣裳をまとい、次のような姿で彼の前に現わ れている。 In an armchair . . . sat the strangest lady I have ever seen, or shall ever see.ミス・ハヴィシャムは、「かつては純白だったろうが、今は褪せて黄色くなった」花 嫁衣裳を身につけた白髪の老女である。ピップには、彼女は「今まで見たうちでもっ とも奇妙な婦人」に見える。彼女は、頭に白いベールをかけ、白くなった髪に花嫁の 花を挿し、首と手にはまばゆい宝石がちりばめられている。その花嫁衣裳の生地は、 サテン、レース、絹でできた上等なものである。そして近くの化粧鏡のあたりには、 時計や、ハンカチや、小さな貴金属や、花や、手袋が無雑作に丸めておかれている。 ディケンズにおいては付属物で主体の性質を暗示するメトニミカルな手法が頻繁に用 いられるが、これを念頭に置き、この一連の高価な「もの」で取り巻かれているミス ・ハヴィシャムが象徴するものをひと言で言うなら、それは植民地の富と規定できる だろう。典型的には、彼女の首と手に光り輝く宝石が、また白い上等のサテンとレー スと絹でできた花嫁衣裳がその富を表象している。しかし、花嫁衣裳を着た老女ミス ・ハヴィシャムはこれから結婚するわけではなく、彼女は結婚できなかったのである 。ずっと以前、彼女は結婚の間際で相手の男に裏切られたのだった。つまり彼女は結 婚詐欺にあい、くだんの男は彼女から相当の財産を巻き上げた上で、逃走した。これ を仕組んだのが、実は、マグウィッチのかつての様々な犯罪の共犯者であり、狡猾にマ グウィッチに罪をかぶせたコンペイソンだった。このようないきさつが作品終盤でマグ ウィッチが登場することにより次第に明らかになっていく。裏切られたミス・ハヴィシ ャムは以来、部屋を閉め切り、昼からろうそくをともし、肱かけ椅子に花嫁衣裳をつ けて座り続けている。 花嫁衣裳をまとった不気味な老女というきわめて非現実的な世界をディケンズはここ で描いている。しかし、この非現実はある明確な歴史の現実を捉えていると読むこと が可能である。すでに何度も見てきたように、植民地の文脈でミス・ハヴィシャムの 富の意味を分析することができる。まず注目すべきは彼女の「色褪せた」花嫁衣裳が 、サテンや絹でできているということである。言うまでもなく、サテンも絹も中国と 密接に結びつく。特に絹は19世紀前半を通じて、紅茶と並ぶ中国の主要な対英輸出品 の一つだった。41したがって、ミス・ハヴィシャムが身にまとっ ていた富は、中国の富であり、それは植民地よりもたらされる富に他ならなかった 。42 しかし、その植民地の富を表象する花嫁衣裳は、朽ちて色褪せ、今や純白ではなく黄 色に変色している。植民地よりもたらされた贅沢な富が、イギリス本国で腐食すると いうこの構造は、自分を紳士に仕立て上げた資産が実はオーストラリア植民地のマグ ウィッチよりもたらされたと知って、穢れていると感じてしまうピップの心の構造と似 ている。つまり、植民地からもたらされる富は、永続性に欠け、穢れており、いずれ 朽ち果てる運命にある。このような論理構造に至る作者の心理に「植民地コンプレッ クス」が働いているのを見るのは困難なことではない。 第三の謎は、作品冒頭部に現われる二人の脱走した囚人の関係をめぐる謎である。一 人はマグウィッチ、もう一人はコンペイソンであるが、マグウィッチがなぜコンペイソ ンに激しい憎悪を抱くのか、というのがこの小説のそもそもの始まりからの大きな謎 である。少年ピップが言いつけ通り、脱走したマグウィッチに食べ物と足かせを切るや すりを持ってきて、ピップからもう一人の脱走したらしい若い男(コンペイソン)を 見たと聞いた時、マグウィッチは興奮し、「ブラッドハウンド("bloodhound")のよう に奴を追いつめて、倒してやる」(I, III, 21)と憎悪をあらわにする。しかし、マグ ウッチもコンペイソンも捕縛され、その後、小説の表舞台から姿を消すので、二人の 関係はその後もしばらく謎として残る。この謎が解かれるのは、マグウィッチがオース トラリアからイギリスに帰還してピップのアパートに転がり込んでまもなくのことで ある。マグウィッチは問わず語りに、ピップとハーバートに自己の来歴を語るが、その 時、初めてマグウィッチとコンペイソンの関係が明らかにされる。「奴の頭蓋骨をこの 火箸で叩き割ってやる」とマグウィッチは言い、その理由を語り始める。それによれば 、コンペイソンはパブリック・スクール出の、教育もある、立派な紳士として通って いた。加えて、容姿も端麗である。これは、少年の頃から浮浪児で、物乞いをしたり 、窃盗を重ねて、刑務所暮らしをしてきたマグウィッチとは対照的な人間像である。マ グウィッチがコンペイソンに初めて会った時、コンペイソンは「懐中時計を持ち、指輪 をはめ、ネクタイピンをつけ、洒落た服を着ていた」("He has a watch and a chain and a ring and a breast-pin and a handsome suit of clothes." [III, III, 346])が、ここで、コンペイソンに付与される立派な「イギリス紳士」のイメー ジにまず注意を払っておこう。それは、作品の中で(黒人)奴隷のイメージが付与さ れるマグウィッチとの関連で重要な意味を有する。コンペイソンはこの時、マグウィッ チを悪事を働く一味として引き込もうとしており、マグウィッチに「お前さん、随分景 気が悪そうじゃないか」と声をかける。マグウィッチは「へい、旦那、もうさんざんで ね」("Yes, master, and I've never been in it [luck] much" [III, III, 346])と答えるが、この時、マグウィッチが「旦那」("master")と言っているのは興味 深い。なぜなら、この二人が喚起する植民地的な意味合いがここでそれとなく姿を現 し始めるからである。景気の良い「イギリス紳士」が一方におり、運に見放され、ま ったく景気の悪い男が他方にいる。そして、マグウィッチは、まるで奴隷がするように 、自己を卑下して、イギリス紳士のコンペイソンを"master"と呼ぶ。そして主人たる コンペイソンは、今、マグウィッチを狡猾に利用しようとしている。実際、コンペイソ ンはその紳士然たる外貌とは異なり、相当の悪党である。 "I went to Compeyson next night, same place, and Compeyson took me on to be his man and pardner. And what was Compeyson's business in which we was to go pardners? Compeyson's business was the swindling, handwriting forging, stolen bank-note passing, and such-like. All sort of traps as Compeyson could set with his head, and keep his own legs out of and get the profits from and let another man in for, was Compeyson's business. . . ." (III, III, 346; italics mine)コンペイソンの仕事は、詐欺、証文偽造、スリであり、要するに、彼は人を欺くこと をなりわいとしている。そのコンペイソンが、マグウィッチを「手下」として、また 「パートナー」として関係を持とうとしている。しかし、コンペイソンは、「決して 足を残さず、利益だけを巻き上げ、罪を他の人間になすりつける。」そして、まさに 罪を着せられたのが、マグウィッチだった。字義通りの意味は以上であるが、植民地 の文脈でこの箇所をメタフォリカルに読むこともできる。というよりも、この一節は 、植民地のメタファをより強く読者に呈示しているように思われる。マグウィッチに 付与される植民地と奴隷のイメージとコンペイソンに付与されるイギリス紳士のイメ ージは、例えば西インドにおけるプランテーションの奴隷と主人の関係を暗示してい るのかもしれない。コンペイソンは、マグウィッチと「手下」であり、かつ「パート ナー」であるような関係を結ぼうとする。それは、本国が植民地と結んだ関係に等し い。植民地をコントロールすべく、イギリス本国は、19世紀に入ってからは、特に白 人居住の植民地で自治政府を認めるようになり、植民地に取り入る政策を取り始めて いた。しかし、コンペイソンは「利益」をすべて巻き上げ、罪を他人に押しつける。 そして押しつけられ、植民地オーストラリアの流刑囚となったのがマグウィッチであ る。つまり、表面的には紳士であるコンペイソンは搾取するイギリス本国政府を表し 、彼の手下であり、パートナーであり、利益を吸い上げられ、罪をなすりつけられる マグウィッチは搾取される植民地や、何の罪も無いのにアフリカから連れてこられて 奴隷となった黒人奴隷をメタフォリカルに表象すると考えられる。 このようにして、マグウィッチの中に搾取される植民地や、あるいは苦役を課される 黒人奴隷を読み込むほどに、実はある矛盾が胚胎してくる。なぜなら、植民地の文脈 で読むと、『大いなる遺産』は明確な植民地主義批判の書となってくるからである。 しかしすでに見たように、ディケンズは『荒涼館』で明らかに、黒人奴隷を救おうと する福音主義の博愛のイデオロギーを揶揄していた。また「エア論争」のところで見 たように、ディケンズはジャマイカの暴動で過度の制裁を断行したジャマイカ総督の エドワード・エアを擁護する立場を取っていた。しかし、この矛盾は、先に見た『パ ンチ』の図の、黒人奴隷に上着の裾を引っ張られようとしているブルーム卿を想起す るなら、ある程度解決する。ブルーム卿は黒人奴隷に対して文字通り、「後ろ向き」 の姿勢を示していた。しかし、彼は裾を引っ張られることによって、いわば、奴隷か ら逃げ切れない中間の領域に閉じ込められていると見ることができる。「エア論争」 でディケンズは、黒人奴隷を切り捨てる身振りを示したが、ディケンズもブルーム卿 と同じように、逃げ切れない領域に閉じ込められていたと考えるなら、『大いなる遺 産』のメタファが暗示する植民地主義批判の謎が解けてくる。端的にいうなら、こと さらに貧困などの国内問題を論じ、奴隷問題を切り捨てようとしたディケンズは、心 の奥に、ブルーム卿と同じ罪の意識を沈下させたのではなかったろうか。この後ろめ たさという罪の意識が、ディケンズの政治的無意識を形作り、彼の心の深部に沈滞し た。ディケンズは「エア論争」で国内の貧困問題を優先し、反・反奴隷運動の姿勢を 明確にした。あるいは、同様の理由で、『荒涼館』で、奴隷制反対運動を皮肉った。 しかし、他方、『大いなる遺産』に、植民地主義批判を忍ばせ、黒人奴隷の悲惨を秘 密裏に暗示している。加えて、私たちは、獄中で死にゆくマグウィッチを前にして、 悔悟するピップを通して、奴隷制に対する贖罪の無意識的な意志を推し測ることがで きる。近代イギリスが残した過去の汚点である黒人奴隷問題は、こうして、ディケン ズにおける「植民地コンプレックス」を形成し、黒人奴隷に対する贖罪の意識が、『 大いなる遺産』においてコンペイソン(=大英帝国)に復讐することを人生の目標と するマグウィッチを造型した。
「エア論争」で明らかになったようにダーウィンはディケンズとは異なり、エアを告 発する側に立っている。ダーウィンは言わば筋金入りの反奴隷制論者だった。しかも ダーウィンの家系には、父方にも母方にも、奴隷制度廃止論者が多かったことが知ら れている。特に、ダーウィンの母方の祖父ウェッジウッドは、『パンチ』の第一図の 箇所でもふれたように、強力な奴隷制反対論者で、彼は自らが経営するウェッジウッ ドという製陶会社で、鎖につながれた黒人奴隷のレリーフの入った陶器を作らせ、そ こに「私だって人間です、私はあなたの兄弟ではありませんか?」("Am I not a man and a brother?")というのちに奴隷解放のスローガンとなるメッセージを刻みつけて いる。一方、ダーウィンの父方の祖父のエラズマス・ダーウィンは、このウェッジウ ッドの行為に共鳴し、それを讃える詩をものした。43 ダーウィン自身もまた折々に奴隷制について発言している。例えば、ビーグル号の航 海中に、その艦長のフィッツロイ(FitzRoy)と奴隷制をめぐり激しい論議を戦わせた 。それによれば、フィッツロイはある夕食の折りに、ダーウィンに次のような話をし た。ある植民地のプランテーションで働いている黒人奴隷たちは、かなりよい待遇を 受けており、奴隷たちもその生活に満足していた。そのプランテーションの農場主は ある時、奴隷全員を集めて、「自由になりたい者はいるか?」と尋ねた。すると、一 人として「自由になりたい」と答えたものはいなかった。これを聞いた、ダーウィン はフィッツロイに、主人のいる前で答えたことが真実を語るわけがない、と反論し、 それは激しい性格であった艦長を激怒させ、ダーウィンは船を降りることを覚悟した という。しかし、結局は、フィッツロイが詫びを入れ、ことなきを得た。44 また、ビーグル号での航海をまとめたダーウィンの『日記』に黒人または未開の原住 民に関する興味深い記述がある。ダーウィンが乗船した時、ビーグル号には、一年前 の航海で艦長フィッツロイが南アメリカの南端のフエゴ島(Tierra del Fuego)から イギリスに連れ帰っていた三人のフエゴ人がいた。フィッツロイは熱心な国教徒で、 これら未開の部族の人間をイギリスで教育し、彼らをまた島に戻してやって、イギリ ス人宣教師の伝道の手助けをさせようとしていたのである。そして、ダーウィンはこ の三人のフエゴ人がたった一年で、驚くほどヨーロッパ化されたことを述べている。 そしてその中の一人のヨーク(York Minster)と名づけられた若者については、もし、 彼が今後もイギリスで生活するとしても、イギリス人とまったく遜色のない生活を送 れるだろうとまで言っている。45未開のいわゆる野蛮人でも、適切な教育を施す なら、きわめて短期間に「文明化」されるということを、ダーウィンはさらにこれか ら40年ほど経た『人間の由来』(Descent of Man, 1871)でも何度か繰り返し 述べている。そしてビーグル号での航海に言及し、フエゴ人や黒人とヨーロッパの白 人との間に驚くべき類似性があることを強調している。 . . . I was incessantlystruck, whilst living with the Fuegians on board the Beagle, with the many little traits of character, showing how similar their minds were to ours; and so it was with a full-blooded negro with whom I happened once to be intimate.46ここでのダーウィンの論点は、それぞれの人種として区別されているものの間には、 差異よりも類似性があることを強調することである。同時に、人種を区別すること自 体が、博物学者がしばしば陥る恣意的な種の分類に他ならないことを述べる。これは 『種の起源』で繰り返し主張されていたことと同様の主張で、究極的にはすべての生 物は無限に連なるきわめて微少な差異の連鎖で結ばれているというダーウィンの根本 理論を傍証するものである。その意味では、ダーウィンが強調する人種間の類似性の 主張は、純粋に学問的な文脈でなされていると見ることができる。いわば、純粋理性 の領域で、ダーウィンは人間の平等を明確に主張した。しかし、生物学者としてのダ ーウィンの人種に関する主張をそのまま額面通りに受け取ることは必ずしもできない 。彼は、ビーグル号の探検において出会った未開の部族を前にして、時に、ある種の 嫌悪感を隠しきれなかったこともまた事実だからである。例えば、先に挙げたフエゴ 人などがそうである。ダーウィンは、ビーグル号に同乗した三人のフエゴ人を深い共 感と驚嘆の念を覚えつつ見ていたことは確かであるが、彼らを現地に戻してやる時に そこで出会うフエゴ人に関しては、かなり率直な非難の目を向けている。最初に現地 でフエゴ人を見た時、ダーウィンは次のように記している。「野蛮人と文明人の差が これほどとは思わなかった……彼らの肌の色は汚い(dirty)銅色である……彼らのふ るまいは卑屈で、表情は不信感を露わにし、驚き、怯えている。」47また 、フエゴ人の間では略奪や盗みが日常茶飯事であることにあきれ、彼らの財産は弓と 矢と槍だけであると述べている。そして、彼らの住居は、岩陰の草むらであり、毎日 、海の浅瀬で何かを拾って食べていると、その生活と文化の低さを強調する記述が目 立つ。48 ダーウィンはまた、ビーグル号の航海の中で、ブラジルにおける奴隷制を口をきわめ て非難している一方で、奴隷制も場合によってはむしろ黒人にとって幸福かもしれな いとふと漏らしたりもしている。1832年4月13日付のダーウィンの日記 ― それは、 彼がビーグル号の航海に出て間もない頃のものであるが ― にそのような奴隷制肯定 ともとれる記述がある。ビーグル号の航海中、しばしばしているように、彼はこの時 、船を降りてブラジル内陸への小旅行をしていた。そして同行した白人の経営する黒 人奴隷の働くプランテーションで、彼は次のような朝の光景に出くわし、ふとつぶや くことになる。 One morning I walked out before daylight to admire the solemn stillness; when it was broken by the morning hymn raised on high by the whole body of the blacks; in this manner do they generally begin their daily work. In such Fazendas as these I have no doubt the slaves pass contented happy lives. (italics mine)49ダーウィンはこの小旅行の行程で、ブラジル農園で働いている黒人奴隷たちの惨状を 見て、農場経営者たちを痛烈に批判している。それにもかかわらず、早朝に労働の前 に黒人たちがいっせいに讃美歌を歌うその光景を目にしただけで、「奴隷たちは間違 いなく満足した、幸福な生活を送っていると思う」と、感じる。しかしその翌日の日 付の日記では、別のプランテーションを見て、「黒人たちは酷使されており、衣服も 悲惨で、日が暮れてもなお遅くまで働かされている」50と、過酷な奴隷制を批判す る。 この未開人と黒人奴隷をめぐってのダーウィンの心の揺らぎはいったい何を意味して いるのだろうか。端的に言うなら、これらのダーウィンの一貫しない記述に窺える心 の揺れ動きは、黒人や、いわゆる異人・野蛮人に対するダーウィンの意識の葛藤を物 語っているに違いない。理性では、奴隷制の廃止を明確に主張し、人種の壁は生物学 的にはない、と考えながら、現実に未開人を見ることによって、ダーウィンは彼らの 文明が明らかにヨーロッパにはるかに劣るものであることを知ってしまう。このダー ウィンにおいてなお払拭できなかった自らのヨーロッパ文明に対する優越感は、皮肉 なことに、ビーグル号に同乗していたフエゴ人に対する賛美を見れば明らかである。 先述したように、ダーウィンはこの三人のフエゴ人に優しい眼差しを注いだが、それ は彼らがイギリスで生活をし、そのことによって彼らの生活習慣が「ヨーロッパ化」 したからである。逆に、ヨーロッパ化していない現地のフエゴ人に彼は冷めたまなざ しを送っている。 ダーウィンの奴隷制反対の立場にも同様の危うい葛藤が窺える。彼はビーグル号の航 海の途中でブラジルに立ち寄った時、ブラジル人たちは黒人奴隷の指を締めつけ、切 り落とす拷問の道具を所有していることが少ないないことを知り驚く。そしてブラジ ルに黒人奴隷があふれており、ブラジルは奴隷制の上に成り立っている国であると知 る。この異国で酷使されている黒人奴隷を目のあたりにして、ダーウィンはいつの日 か、これらの黒人奴隷たちが自由になり、この国の支配者になる日が来ることを願う 。しかし、そういう日が来て、彼らが自分の権利を主張できるようになっても、彼ら が受けたひどい仕打ちのし返しをすることがないようにと思う。51奴隷 たちは拷問にかけられ、指を切られ、それでもなお復讐することはよくないと考える ダーウィンは、キリスト教的博愛の精神にのっとって、言っているには違いない。し かし、ダーウィンは、彼の祖父のウエッジウッドがその陶器に刻んだように黒人たち を「兄弟」と考えていたとするなら、「仕返しをすることのなきように」と淡々とし て冷静でいられたであろうか。彼がブラジルの奴隷たちに注いだ眼差しは、当時とし ては並外れて優しかったことは間違いない。しかし、その眼差しに込められていたの は、憐れみの眼であると同時に、その陰に隠されたヨーロッパ人としての、あるいは 白人としての優越心だった。それは彼の言葉の使用にも如実に現われており、彼はビ ーグル号の航海を記した日記の中で、「野蛮人("savage")」、「野蛮な ("barbarous")」などの差別的な言葉を何のためらいもなく、頻繁に使用している。 今まで見てきたダーウィンの日記における記録はほぼすべて1832年からのものである 。そしてこの時期は、まさに本国のイギリスにおける奴隷制の廃止(1833年)の時期と ほぼ重なる。同時にダーウィンのみならず、ダーウィン一族がかなり積極的な奴隷制 廃止論者であったことを想起するなら、イギリスにおける奴隷廃止運動の最良の部分 がダーウィンにおけるような「憐れみ」と「優越心」という複雑な葛藤のもとに成立 していたのではないかと推測できる。ここにおける相反する意識の葛藤を、仮りに、 「奴隷コンプレックス」と名づけるとするなら、このコンプレックスは、先行する章 で検討した「植民地コンプレックス」と近い関係にあることがわかる。なぜなら、「 植民地コンプレックス」は奴隷を制度化し、植民地で搾取してきたというきわめて最 近の行為に対する良心の呵責に由来しているし、他方、「奴隷コンプレックス」は、 黒人奴隷と「兄弟」にはなれないというもどかしさ、そしてその裏に隠された白人の 優越心を反映させているからである。そして両者を繋ぐ共通点は、植民地と、黒人奴 隷であり、そこから引き起こされる葛藤である。この葛藤、すなわちコンプレックス は、罪の意識とそれを否定しようとする隠蔽された心理の動きである。いずれにして も、ディケンズにとって、『パンチ』の漫画作者にとって、そしてダーウィンにとっ て、あるいは彼らと時代を共有した多くのヴィクトリア朝の人々にとって、植民地、 黒人、奴隷という言葉は罪の意識と、それを打ち消そうとする相反する心理作用を惹 起したのではなかったろうか。これはフロイトの言う無意識と抑圧という構造に似て いる。ここでの無意識とは、植民地と黒人奴隷にかかわるものすべてであり、それを 抑圧するものが、人間の良心であり、ヨーロッパ人の優越心である。 以上の考察より明らかになった「植民地コンプレックス」あるいは、「奴隷コンプレ ックス」という概念を手がかりに最後に、無色透明の科学的記述に見えるダーウィン の『種の起源』のある部分を検討してみたい。
『種の起源』においては、徹底的に透明な記述が志向されている。しかし、フロイト に倣うなら、次のように言えるかもしれない。ダーウィンに「奴隷コンプレックス」 があったとしたら、そのコンプレックスという意識を隠蔽することはできない。コン プレックスは必ず出口を探し、無意識を解放しようとするからである。そして『種の 起源』はそのコンプレックスが発現する場となったと考えられる。 これまでの考察で、ダーウィンにおいて、彼を取り巻いていた時代状況との関係で、 コンプレックスを生じさせていたものは、奴隷(制度)であった可能性を指摘した。 果たして、『種の起源』において、奴隷制度が描かれている。しかも、それはいかに もフロイト的な「転移」によって描かれている。なぜなら、『種の起源』の奴隷は、 人間の奴隷ではなく、アリにおける奴隷制だからである。巣を作り、集団生活を営む 社会性昆虫("social insects" [VII, 259])52であるアリは、ハチと並ん で、古来より人間社会の縮図(メタファ)として捉えられてきたことは改めて指摘す るまでもない。 『種の起源』でアリを記述した箇所は、生物の「本能」もまた自然選択を受けること を論じた第7章の中にある。ダーウィンはここで生物の本能を述べるにあたり、『種の 起源』でいつもそうするように、膨大でかつ詳細な具体例を列挙する。このような具 体例に依拠した、ベーコン流の経験主義的な傍証の手法は、ダーウィンがその著作の 着想において多くを負ったとされる『人口論』のマルサスの手法と共通するものであ る。言い換えるなら、当時の統計学の手法に通じる方法論に沿って、ダーウィンは論 を進めている。極端に言うなら、理論1 に対して、例証としての事実は100を超える 比率で、ダーウィンは『種の起源』において、飽くことなく、事実を延々と積み上げ ていく。本能を論じた第7章に関しては、例えば、トリの渡り、カッコーの巣借り、イ モムシの寝床作り、アリマキのミルクの分泌、ポインター(猟犬)やシェパードの特 有の行動、宙返りバトの宙返り、奴隷を作るアリ、ハチの巣作り、等々を扱っている が、その中でも特に紙面を多く割き、詳細に論じているのはアリとハチに関する部分 である。したがって、この二種の昆虫に特にダーウィンが興味を惹かれていることが 推測できるのであるが、なぜ興味を覚えているのかを推量するなら、やはりそこに人 間社会の縮図を見る思いがしたからであろうと思われる。例えば、ハチの巣作りを論 じて、ダーウィンは次のように述べている。ハチの巣の形態は、マルハナバチ (humble-bee")、メキシコ・メリポナバチ("Mexican Melipona")、ミツバチ ("hive-bee")という種によってそれぞれ異なっており、その形態は、円柱から、球体 、そして球を潰した形の二層の六角柱様のものへと変化(進化)する。したがって、 巣作りという本能にも中間的な段階や中間的な形態("intermediate gradations" [VII, 257])があることがわかる。段階があり、中間的な形態があるならば、それは 自然淘汰を受けているというのがダーウィンの理論であり、したがってダーウィンは 本能も自然選択の作用を受けていると結論する。ミツバチの巣作りに関して、ダーウ ィンはおよそ次のような趣旨のことを述べる。 私の観察したところでは、ミツバチの巣のはじめの蝋(ロウ)の形はフード(頭巾) 型である。注意すべきは、ミツバチの蝋を使っての壁の作り方で、彼らはまず最終的 に出来上がる壁の厚さの10倍から20倍の厚さの壁を作り、それを薄くしていく。これ はちょうど、煉瓦職人("masons")の壁作りと同じである。煉瓦職人は壁を作るとき、 てっぺんの部分にたっぷりセメントを盛り上げ、それを削ったりのばしたりして薄く して、それに煉瓦を積み上げて、壁を作る。こうすることで煉瓦と煉瓦をつなぐセメ ントの部分をきわめて薄くする。こうして、煉瓦職人がセメントを節約するように、 ミツバチは貴重な蝋を節約する。最終的には、壁の蝋の厚さは400分の1インチになり 、底面の厚さはその2倍になる。しかも、このような巣作りは、たくさんのハチのいっ せいの共同作業によってなされる。(VII, 253) ここで、ミツバチが煉瓦職人になぞらえ、擬人化される。無論、ミツバチがいかに貴 重な蝋を節約し、巧みに巣のセルとセルの間の壁を薄くしているかをわかりやすくす るために、ダーウィンは煉瓦職人のメタファを用いているのであるが、ここでは、ミ ツバチを人間の比喩で捉えていたという事実関係をまず確認しておこう。 『種の起源』では、このハチの巣作りの箇所の前後に、奴隷アリの話と、アリにおけ るカースト制度の話が記載されている。奴隷化するアリの話でもっとも興味深い部分 は、それはちょうど白人が黒人を奴隷化したように、異なった種間のアリで行われる ことであり、同種のアリでは生じないということである。しかもその時、奴隷になる のは「黒アリ」("Formica fusca")である。「奴隷は黒くて、彼らの赤い色の主人の 半分の大きさも無い("The slave are black and not above half the size of their red masters.") [VII, 244]」とダーウィンは述べている。ここで、アリが「 奴隷」と「主人」という完全に人間の奴隷制度のメタファで描かれていることは注目 に値する。このアリにおける主人と奴隷の関係を最初に発見したのはピエール・ユベ (Pierre Huber)で、彼はフォルミカ・ルフェセンス("Formica rufescens")という 赤いアリが黒アリを奴隷化する習性があるのを発見した。それによると、「このフォ ルミカ・ルフェセンスというアリは完全に奴隷("slave")に依存しており、奴隷がい なかったら、フォルミカ・ルフェセンスという種自体が一年で絶滅するだろう」 (VII,243)ほどである。 ところで、『種の起源』はビーグル号の航海から帰った直後の1837年からノートが作 られ始め、20年を超える研究の歳月を経て、ウォレスの論文の刺激を受けて予定より も早く、1859年に要約を記した形で出版されている(それでも、ペンギン版でほぼ 400頁の大作であるが、ダーウィンはもともとはもっと大部の著作にする予定だった )。53『種の起源』の執筆に取りかかる直前の時期、 イギリスは、1807年に奴隷売買を禁止し、1833年には世界に先駆けて、イギリス帝国 内での奴隷制の廃止に移行した。かつては、「王立アフリカ会社」で世界の奴隷貿易 を支配し、西インドの奴隷プランテーションからもたらされる砂糖という芳醇な富を 享受したイギリスだったが、ともかく奴隷制を世界で初めて廃止した人道的な文明国 になったということは、イギリス人の誇りをくすぐったに違いない。その中には、当 然、一族を挙げての熱心な奴隷制廃止論者であったダーウィンも含まれる。したがっ て、さしたる深読みをする必要なく、「奴隷がいなかったら、フォルミカ・ルフェセ ンスというアリは一年で絶滅するだろう」というユベを受けたダーウィンの記述には 、いまだに奴隷制を維持しているアメリカを初めとする欧米各国への皮肉が見て取れ る。 さて、ハチやアリの本能を扱った『種の起源』の第7章は、本能も自然選択の作用を受 けて、進化・変化してきたことを論じている。そのためには、ある同じような行為に 導く本能の働きに差異があり、中間的な段階があることをダーウィンは示さなくては ならない。ダーウィンが、ハチの巣作りにおいて、中間的な形態があることを立証し たことはすでに述べた。ダーウィンは同様にして、アリの奴隷化する本能にも差異や グラデーションがあると指摘している。この時、比較されているのは、奴隷に完全に 依存するフォルミカ・ルフェセンスというアリと、イギリスの赤アリ("Formica sanguinea")である。両者には、奴隷化する形態に明らかな差異がある。フォルミカ ・ルフェセンスという赤いアリの巣の社会では、古い巣を捨てて、移動するのも、移 動を決定するのも、実際に主人のフォルミカ・ルフェセンスを顎でくわえて運ぶのも 、すべて奴隷アリの黒アリである。しかも、この奴隷アリの主人であるフォルミカ・ ルフェセンスは自分のすぐ近くに大好物のえさが十分にあっても奴隷アリがいないと 食事ができず、餓死する。逆に、そのような餓死寸前になった主人のアリの群れに、 奴隷アリを一匹放つと、その奴隷アリは「かいがいしく世話を始め、フォルミカ・ル フェセンスを餓死から救う」(VII, 244)。まるで、植民地からもたらされる富がない と、もはや成り立たなくなった帝国主義時代のヨーロッパ諸国の経済を暗示するかの ような記述である。しかし、イギリス在来種の赤アリ("Formica sanguinea")は、フ ォルミカ・ルフェセンスとは少なからず、その奴隷化する形態が異なる。ダーウィン はイギリスにも奴隷を作るアリがいるということを、大英博物館のスミス(Mr.F. Smith)の報告により知るが、その時ダーウィンは、「奴隷を作るという異常で忌まわ しい("extraordinary and odious")本能に関して、半信半疑であった」(VII, 244) 。しかしそれが事実であることを、ダーウィンは、自らの観察によって確かめる。そ れによれば、イギリスにいる赤アリの巣を掘り返すと、中には必ず数匹の黒い小さな 奴隷アリがいる。この奴隷となっている黒アリは一種の中性昆虫で、同種の黒アリで も生殖能力のある雄アリと雌アリは奴隷化されないこともわかる。また、イギリスの 奴隷アリは忠誠心が強く、巣を乱すものがいると主人のアリと一緒になって闘うし、 巣が危うくなると主人といっしょに幼虫やさなぎをくわえて必死に逃げ、幼虫やさな ぎを安全な場所へ運ぶ。これらのことから、ダーウィンは次のように結論する。奴隷 となった黒アリは、育った巣を我が家と心得ているらしく、「奴隷は巣をまったく居 心地がいいと考えていることは間違いない」("Hence, it is clear, that the slaves feel quite at home." [VII, 244-45])。 このようにして、フォルミカ・ルフェセンスというアリの奴隷制とイギリスのアリの 奴隷制の違いが明らかにされていく。前者は、完全に奴隷任せであり、たくさんの奴 隷を使い、自分では巣も作らないし、移動もしないし、自分で食べないし、子育ても しない。奴隷がいなかったら絶滅するまでにその奴隷化が極端に進化している。他方 、イギリスの赤アリの社会では、一つの巣にいる奴隷アリの数が少なく、移動は赤ア リが主導権を持ち、移動の時は、赤アリが奴隷アリを運ぶ。このようなことは同様に 、スイスの赤アリでも見られる。そのスイスのアリもイギリスにいる赤アリと同様に 奴隷狩りに出かけたり、食料を調達してくる。そしてスイスの赤アリは奴隷アリと共 同で巣を作るが、イギリスの赤アリは奴隷を使わず自分だけで巣を作る。したがって 、ダーウィンは、フォルミカ・ルフェセンス、スイスの赤アリ、イギリスの赤アリを 比較すると、この三種のアリでは、イギリスの赤アリが奴隷からもっとも奉仕されて いないと述べ、奴隷化する本能の度合いにグラデーションがあることを指摘する。こ うして、アリの奴隷制において、不完全な奴隷制から完全な奴隷制に至るまでの段階 があることを述べることによって、ダーウィンはこの奴隷化の本能もまた他の本能と 同様に自然選択の作用を受けていると結論する。 以上のことが『種の起源』においてダーウィンによって説明されているアリの奴隷制 の物語である。これは少なくとも表面的には、純粋に科学的な意図のもとに書かれた 記述である。しかし、ここにおいて、ダーウィンがあまりにも擬人法を使用している ために、単なるアリの奴隷制の物語を超えていこうとする(無意識的な)意志の働き を感じないわけにはいかない。擬人法とは、例えば、「主人と奴隷("master" & "slave")」、「奴隷狩り("slave-making expedition")、「共同体 ("communities")」などの表現に現われている。擬人法は、不可避的に、アリの奴隷 制の物語を、人間の奴隷制の物語であるかのような錯覚を生み出す。これは、ダーウ ィンは奴隷アリのことを、ただ「奴隷("slave")」としか表記していないのでなおさ らである。ダーウィンはのちに『人間の由来』(1871年)で明らかにするように、人 間を完全に『種の起源』で展開した理論の中に組み入れることになる。その点で、ダ ーウィンは、人間の脳の発達だけは他の生物とは別で、人間を特殊な存在であると考 えたアルフレッド・ウォレスと大きく異なっていた。54つまり、ダーウィンは生物 における現象、ないしは生物の一般法則は基本的には、人間にもあてはまると考えて いた。そのようなダーウィンの前に、他の種のアリのさなぎをさらってきて、奴隷化 するアリが現われる。その光景は、アフリカの黒人がヨーロッパの白人によって、西 インド諸島に運ばれ奴隷化された歴史的事実をまさに彷彿とさせたに違いない。しか も、アリはすでに人間の縮図であるとの伝統的な文化のコードが存在している。奴隷 制廃止論者であったダーウィンが感じたであろうジレンマ、葛藤は、したがって、容 易に想像できる。先にも見たように、奴隷を作るアリの存在を知ったダーウィンは、 それを「異常で忌まわしい本能」だと述べている。しかし、このように生物の現象を 前にして、ダーウィンが主観的感想を漏らすことは、『種の起源』においてはきわめ て稀なことである。ダーウィンは、『種の起源』から禁欲的なまでに主観を排除して いるからである。このような禁欲的な緊張が解けるのは、『種の起源』の有名な結末 部だけであると言っても過言ではない。そこでダーウィンはめずらしく、ロマンテッ クな感情にまかせて「たくさんの種類のたくさんの植物で覆われた川岸」では「鳥は 木の枝の上でさえずり、様々な昆虫が飛び交い、じめじめした土の中ではミミズが這 い回っている」と述べ、「単純なものから、きわめて美しくきわめて素晴らしいもの ("endless forms most beautiful and most wonderful")が無限に生成し、いまも なお生成し続けている」と締め括っている(VII, 456-60)。ダーウィンは、自分が見 いだした生物界の自然の法則をきわめて「美しい」と感じていたことは間違いないが 、彼は、「美しい("beautiful")」とか「素晴らしい("wonderful")」という言葉を 使うのを極力控えている。しかし、実は、ダーウィンは結末部以外でも、ごく稀に感 情を漏らすことがあり、それがアリの奴隷制を前にした時である。55その 時、ダーウィンは例えば「奴隷を作るという驚くべき本能」("the wonderful instinct of making slaves" [VII, 246])と述べ、"wonderful"という語を使用し ている。"wonderful"という語は周知のように、「驚くべき」と「素晴らしい」とい う意味を含有しており、奴隷制との文脈で考えるなら、このようなアンビヴァレント な語を使用したということは若干、不用意なイメージを読者に与える。もしかしたら 、ダーウィンにとっては、アリにおける奴隷制と人間の奴隷制との生物学的な一致は 、「驚くべき」であるとともに「素晴らしい」ものに見えていたかもしれないことを 、私たちは、両義的な言葉の使用の裏側に読み取ることができる。少なくとも、生物 学者としてのダーウィンにとって、アリとヒトがここまで酷似していることは「素晴 らしい」ことであった可能性は充分にある。なぜなら、ダーウィンの分岐の理論や系 統の法則は、ヒトの祖先をはるかかなたまで辿っていくなら、もっとも単純な生物に 至る過程で、アリもまた通過点になることを示しているからである。すべての生物は 無限に微妙な差異の連鎖でつながっているというのが、『種の起源』から導き出され る重要な結論の一つである。したがって、アリとヒトにおけるこのような「驚くべき 」一致は、彼の理論の正しさを傍証するという点で「素晴らしい」ものであったかも しれない。これが生物学者としての、アリの奴隷制に関する思いであった。しかし、 奴隷制廃止論者としてのダーウィンは、「奴隷を作るという異常で忌まわしい本能」 (VII, 244)をそこに感じ取る。ここでも主観的な感情が吐露されていることが注目さ れる。冷静な科学者ダーウィンがその落ち着きを失った瞬間である。このように、ア リの奴隷制をめぐって矛盾に満ちた言語が交錯する。アリの奴隷を作るという本能は 「驚くべき」であると同時に、アリとヒトの奴隷制の一致は「素晴らしい」ようにも 思われる。しかし、それは「異常で忌まわしい」。このような意味の分裂は、ダーウ ィンにおけるイデオロギーの分裂を示している。科学者としてのダーウィンは生物に おける奴隷制が、ある普遍的な生物の真実を語っていることを知った。そこで、ダー ウィンにおける純粋科学のイデオロギーは、生物の奴隷制を観察し、正確に記録せよ 、とダーウィンを促す。しかし、奴隷制廃止論者であったダーウィンにおける福音主 義的博愛のイデオロギーが彼をして、生物における奴隷制に嫌悪感を表明させた。 この肯定と否定というダーウィンにおける解決しがたい葛藤は、彼の(無)意識にお いてある種の合理化を生むことになる。それは「奴隷は幸福かもしれない」という正 当化となって現われる。というのも、彼は、奴隷となった黒アリに関して、「奴隷は 巣をまったく居心地がいいと考えていることは間違いない」と述べているからである 。このような合理化は、まさしく、前の章で見た、ブラジルの奴隷たちを目にした時 のダーウィンの心の動きとまったく同じである。前に見たように、早朝の労働の前に 黒人たちがいっせいに讃美歌を歌う光景を目のあたりにしたダーウィンは、「奴隷た ちは間違いなく満足した、幸福な生活を送っていると思う」と感じるからである。肯 定と否定、そして合理化という心の一連の動きは、ここに強烈なコンプレックスが働 いていたことを示している。すなわち『種の起源』の奴隷アリの記述の裏側には、前 の章で論じたダーウィンの「奴隷コンプレックス」が存在していると見ることができ る。無論、ビーグル号の航海で生じた「奴隷コンプレックス」は、黒人奴隷と真の「 兄弟」にはなれないというダーウィンのもどかしさに由来しており、ここでの、純粋 科学のイデオロギーと福音主義のイデオロギーとの相克から生じる葛藤とは少し意味 が違っている。しかし、この科学と博愛主義の対立からもたらされる葛藤=コンプレ ックスも、ダーウィンの黒人奴隷に対する「憐れみ」と、ダーウィンの白人としての 「優越心」との相克から生じる葛藤も、その根本の原因は、イギリスが植民地で組織 的に黒人奴隷を作り出し、そして利用し、搾取したという歴史の事実とそこから不可 避的に生じた罪の意識に求められる。したがってダーウィンが『種の起源』でアリの 奴隷制に瞠目したその科学者としての視点の裏に、ダーウィンにおける強烈な「奴隷 コンプレックス」を探りあてることができる。
本稿は、1860年からその翌年にかけて連載されたディケンズの『大いなる遺産』と、
1859年に出版されたダーウィンの『種の起源』を繋ぐ糸の可能性として植民地の黒人
奴隷を呈示する。そして、黒人奴隷をめぐってディケンズとダーウィンが無意識下に
隠蔽した葛藤(コンプレックス)の存在を解明してきた。『大いなる遺産』も『種の
起源』も黒人奴隷を明確に作品の表層で取り扱っていない。しかし、それはディケン
ズが流刑囚マグウィッチの中に、そしてダーウィンはアリの奴隷制度にその奴隷と植
民地に由来する葛藤を封じ込めたからである。私たちは、盛期ヴィクトリア朝を体現
した科学者と文学者の中に、イギリスがかつては国家的プロジェクトとして推進した
黒人奴隷制度をめぐるヴィクトリア朝人の肯定と、否定、あるいは合理化という矛盾
に満ち、振幅を繰り返す、とまどいの言説を見ることができる。
|
